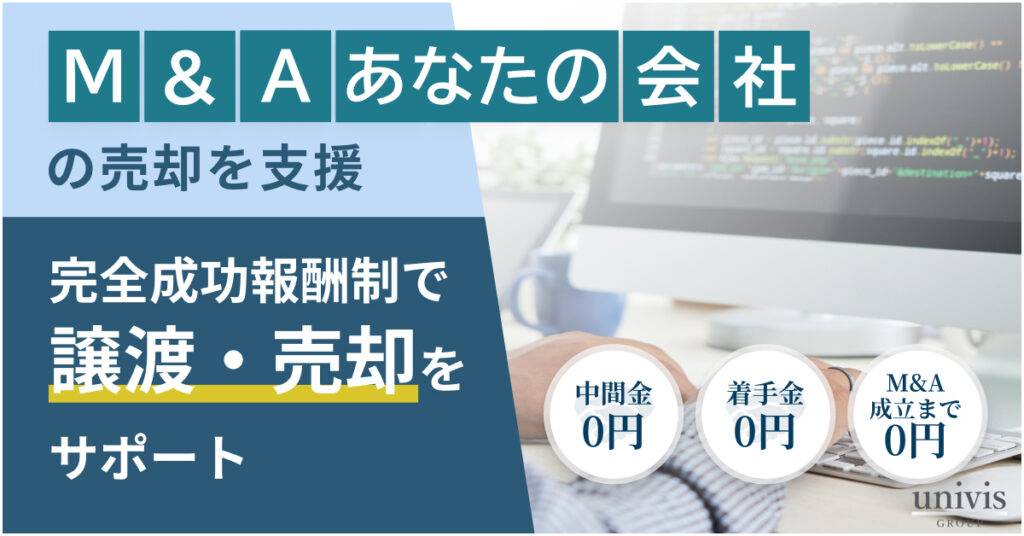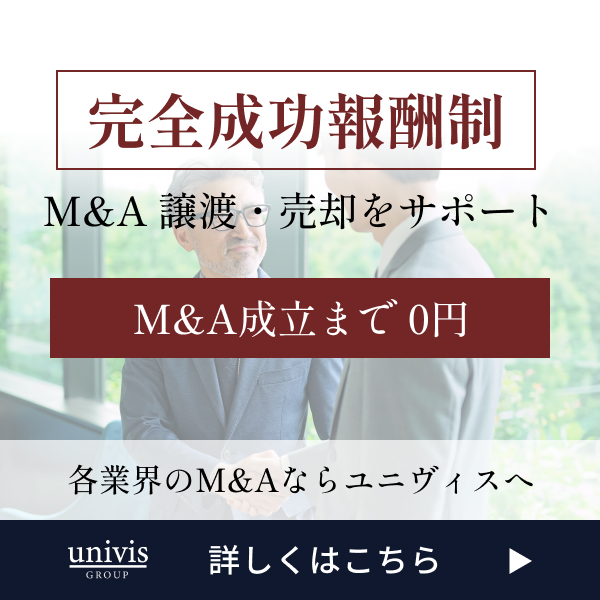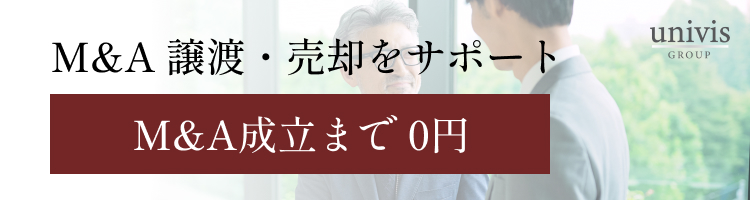M&Aのクロージングとは?実施の流れから注意点まで徹底解説!

「クロージングって何だろう?」
「どのような書類を準備すれば良いのだろう」
M&Aについて調べていて、クロージングという言葉を目にしたことはありませんか?
クロージングはM&Aの成否を決定づける重要な局面ですが、あまり詳細に解説されてはいません。
そこで今回はクロージングについて、実施の流れと注意すべきポイントについて紹介します。
この記事を読めば、クロージングについての基本的な理解を抑えることができますよ!
目次
1. そもそもクロージングとは?

クロージング(Closing)はその名の通り、手続きを「終わらせること」を意味します。
M&Aでは、最終契約を締結した後に、M&Aの対象となる会社または事業の経営権を売り手から買い手へと移転させる手続きのことを指します。
2. クロージングの流れ
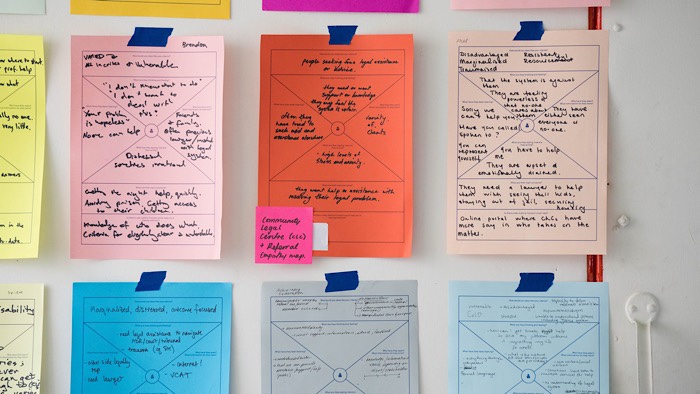
クロージングの流れは、採用するM&Aの手法によって異なります。
そこで今回は、主要なM&A手法に対して、手続きの流れと必要書面について紹介します。
なお、クロージングの諸手続きは、会社法等の法令に従って行う必要があり、以下に紹介するのはいずれも法令上の原則規定に基づいたものです。
しかし、会社法は各社の定款に大きな裁量を認めている(定款自治)ため、会社によっては採るべき手続きが異なる場合があります。
そのため、クロージングを実行するにあたっては定款をよく確認し、内容に不安があれば必ず専門家に相談するようにしましょう。
(1) 株式譲渡の場合

株式譲渡は、株式の移転によって行うM&Aです。
他の手続きと比較すると手続きが簡便であることから、主に中小企業において用いられることの多い手法です。
クロージング手続きとしては、株式の譲渡とその対価の支払いのみを行います。
#1:クロージングの流れ
大半の中小企業は、定款によって株式の譲渡については制限が設けられています(制限譲渡株式)。
そのため、会社法の規則に則り、株式の譲渡については取締役会または株主総会によって譲渡承認を得る必要があります。
譲渡承認は、原則として、取締役会設置会社であれば取締役会、それ以外の会社であれば株主総会が行いますが、定款によって別に定めれられている場合もあります。
この譲渡承認手続きが適法に行われていない場合、その譲渡は譲渡当事者間では有効ですが、会社との関係では無効となってしまいますので、注意しましょう。
買い手側は、各種書類を確認したのち、対価の支払いと、株主名簿の書き換えを行い、会社の実印や通帳等の経営に必要な各種資料も同時に引き渡されます。
最後に、買い手側で臨時株主総会を実施して新役員の決定を行い、さらに取締役会で新しい代表取締役を選任します。
一見これらの手続きは煩雑に思われますが、中小企業であれば全ての手続きが1〜3日ほどで完了します。
#2:必要なもの
株式譲渡によるクロージングにおいて準備すべき書面は、主に以下の通りです。
- 株主名簿
- 株式譲渡承認請求書・承認機関による承認書
- 取締役会議事録
- 売主証明書
- 株主譲渡委任状
先ほど述べたように、承認書は特に重要であるため、法令と定款を確認の上、適法な承認書の作成を行いましょう。
(2) 事業譲渡の場合

事業譲渡は、会社の一部の事業や資産を売買するM&Aです。
主に、会社の事業のうちの一部のみを売却又は買収する場合に用いられる手法で、大企業の場合であれば事業の一部を独立させる場合にも用いられます。
株式譲渡と比べるとクロージング手続きが煩雑ですが、多くの場合に用いられる手法ですので、しっかり確認しましょう。
#1:クロージングの流れ
事業譲渡におけるクロージング手続きとして、まずは株主総会による特別決議を経る必要があります。
特別決議とは、議決権株式総数のうち過半数以上の株主が出席し、その出席株主のうち3分の2以上の賛成を得る株主総会の決議をいいます。
買い手は事業の全部を買収する場合に、売り手は事業の全部売却または重要な事業の一部売却(事情譲渡の価額が総資産の5分の1以上)の場合に特別決議が必要です。
次に、株式譲渡の場合とは異なり、事業譲渡の場合は資産や契約の各当事者に事業譲渡の承認を得なければなりません。
たとえば、不動産登記や取引先との契約、官公庁による許認可、従業員との労使関係等は一旦全て白紙に戻り、あらためて合意形成をします。
そのため、株式譲渡の場合とは異なりクロージング手続きに時間がかかってしまうことに注意してスケジューリングをする必要があります。
例外として、株主総会の決議が必要とならない場合があります。
簡易事業譲渡や略式事業譲渡にあたる場合は株主総会の特別決議は不要です。
#2:必要なもの
事業譲渡によるクロージングにおいて準備すべき書類は、主に以下の通りです。
- 事業譲渡に関する取締役会決議書
- 事業譲渡契約書
- (必要があれば)公正取引委員会への届出
- 株主に対する通知・公告
- 株主総会の特別決議書
- 各種契約の名義変更、許認可手続
このように、株式譲渡の場合と比べると準備すべき書面の数も多く、専門性も求められるため、これらは専門家に依頼するほうが安全だといえるでしょう。
(3) 第三者割当増資の場合

第三者割当増資は、新株を発行してこれを特定の第三者に買い取らせることにより、経営権を一部(または過半数以上)移転させるものです。
この手続きは、原則として取締役会決議のみで行えるため、迅速なM&Aが可能であるとともに、売り手が緊急に事業資金を必要としている場合に多く用いられます。
その一方、会社の経営権の一部が移転するという重大な決定であるにも関わらず、株主がその意思決定に参加できないというデメリットがあります。
そこで会社法は以下に述べるように、株主総会の特別決議を経るべき特則を設けているため、注意する必要があります。
#1:クロージングの流れ
企業が定款で株式譲渡について制限をかけている(制限譲渡株式)場合、株主総会の特別決議が必要です。
中小企業はほとんどの場合に制限譲渡株式を発行しているため、原則としてクロージングにあたっては特別決議を経る必要があります。
株式譲渡について制限のない公開会社の場合であれば、基本的には取締役会の決議のみでクロージングを行うことができます。
ただし、有利発行(相場よりも安い株式の付与や、無償譲渡)の場合には、特別決議を経なければなりません。
これは、先ほど述べたように、第三者割当増資によって既存株主の利益を害する恐れが大きいことから、既存株主の意思を確認する必要があるためです。
#2:必要なもの
第三者割当増資において準備すべき書面は、主に以下の通りです。
- 募集要項を定めた取締役会決議書または株主総会特別決議書
- 募集事項の通知・公告
- 総数引受契約締結書
- 株主名簿
- 株式発行に係る登記
第三者割当増資については、既存株主保護の観点から法改正が頻繁に行われています。
そのため、最新の法令に準拠して手続きを進めるようにしましょう。
3. クロージングで注意すべきポイント

ここまではM&Aのクロージングについて、手続きの流れと必要な書面等について紹介してきました。
それでは最後に、クロージングを行う上で注意すべきポイントについて2つ紹介します。
2つのポイントを抑えて、クロージング手続きをより円滑に進められるようにしましょう。
(1) 余裕をもったスケジューリングで行う

M&Aのクロージングを実施する場合には、余裕をもったスケジューリングで行うようにしましょう。
最も簡易な手続きである株式譲渡によるM&Aであっても、株主名簿等の書面を準備する必要があり、多くの中小企業はこうした書面があらかじめ整理されているわけではありません。
また、事業譲渡によるM&Aであれば関係各者との契約を更新する必要があるなど、予想外の期間が必要となる恐れがあります。
そのため、クロージングを迎えるにあたっては、採用するM&A手法に合わせて余裕をもった期間設定を行うようにしましょう。
(2) 専門家に依頼する

M&Aのクロージングを実施するにあたっては、専門家に依頼するようにしましょう。
以上紹介してきたように、M&Aのクロージング手続きは会社法に則り、会社の定款を調査して解釈を行う必要があります。
しかし、会社法は商法から独立して制定されてまだ日が浅く、諸法令のなかでも特に改正の多い法律のため、専門的な法的観点からのチェックが欠かせません。
その一方で、全ての弁護士がM&A業務に対応できるわけではないため、経験豊富なM&A仲介業者によるアドバイスも受けるべきであるといえます。
4.ユニヴィスグループのアドバイザリー業務実例

M&Aのクロージングについて詳しく説明してきましたが、ここで弊社ユニヴィスグループのM&Aアドバイザリー業務の実例を紹介します。
以下の買い手、売り手によるM&Aにおいて東証1部製造業側のM&Aアドバイザリーを実施しました。
- 買い手:東証1部製造業
- 売り手:ソフトウェア開発業
買収対象となる企業のリストアップ及びその提案を行った上で、買収のスキーム策定、シナジー効果のプランニング、及び交渉のサポートを行いました。
また、外部のデューデリジェンス及び価値算定を行うコンサルティングファームと連携し、案件の成約のサポートを実施しました。
5. まとめ
今回はM&Aの最終局面であるクロージングについて紹介しました。
クロージング段階はM&Aの完成も目前ではありますが、この手続きに不備があるとこれまで準備してきた全てが台無しになってしまう、非常に重要な局面です。
そのため、M&Aの実施を考えるにあたっては、あらかじめこのクロージングまで見据えた計画を策定するようにしましょう。
この記事がその一端となりましたら幸いです。
ユニヴィスグループが御社のM&Aをサポートします!

M&Aの成功には、税務・法務・財務の専門知識が欠かせません。
M&Aを始めて検討される企業には、M&Aの実務を担当できる人材が不足していることも多いです。
弊社ユニヴィスグループは、御社のM&A業務を一気通貫でサポートできる体制が整っています。
大きな投資がかかるM&Aで失敗しないために、弊社がサポートいたします。
以下のリンクからご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。