「事業譲渡って何?」
「どのような手続きが必要なの?」
M&Aについて調べていて、事業譲渡という言葉を目にしたことはありませんか?
会社自体の合併や買収ならまだしも、「事業」の譲渡というのはあまりイメージが湧きませんよね。
そこで今回は事業譲渡について、具体的な手続きや会計・税務上の処理方法など、基礎から具体的に解説しています。
この記事を読めば、事業譲渡に関する不明点はなくなりますよ!
1.事業譲渡とは?

事業譲渡とは、会社が取引行為として、「事業」を他人に譲渡することをいいます。
たとえば、食品事業とアパレル事業を営んでいるA社が、食品事業だけをB社に譲渡するような場合を指します(一部譲渡)。
譲渡の対価としては金銭が一般的ですが、譲受人が株式会社である場合には、その会社の発行する株式であってもかまいません。
なお、この事業譲渡は、会社法改正以前には「営業譲渡」と呼ばれていました。
規制の実態については変化がなく、用語の整理がなされたにすぎないため、従来の理論や判例の解釈に変更はないとされています。
(1)事業譲渡に関する法律

事業譲渡については会社法467条以下に規定がありますが、実は会社法上の特別な行為というわけではありません。
というのも、そもそも会社の保有する債権や債務は、それぞれ個別に譲渡や引受を行うことができるため、これを事業単位で一括して行うことを「事業譲渡」と称しているにすぎないのです。
そのため事業譲渡に際しては、会社法上の規定だけではなく、民法の一般規定にも従う必要があります。
たとえば、相手方が譲渡会社の債務を免責的に引受ける場合には債権者の承諾が必要となります(民法467条)。
(2)「事業」の意味

事業譲渡が有効に成立するためには、譲渡の対象財産が「事業」としての実態を備えている必要があり、従来よりその意義が問題となっていました。
この点、最高裁は事業譲渡の要件をおおよそ以下のように定義しています。
具体的には、以下のように考えてみましょう。
まず①についてですが、たとえば事業を休止していた会社がその事業に使っていた財産を寄せ集めて譲渡しようとした場合、その事業は「有機的一体として機能する財産」とはいえないため、会社法上の譲渡は有効に成立しません。
また②については、譲受人が、譲受した土地や工場などを売り払ってしまった場合には、事業活動を受け継いだとはいえず、こちらも会社法上の事業譲渡とはいえません。
なお、会社法上の事業譲渡の要件として③が必要かについては今も議論が分かれていますが、後述するように、いずれにせよ譲渡人は譲渡後に競業避止義務を負います。
2.事業譲渡のメリットとデメリット

ここまでは事業譲渡に関する法律上の根拠や、定義について説明しました。
これらの内容は抽象的な概念であるため、読んでいてもいまいちピンとこなかった方もいるかもしれません。
以下からは、事業譲渡のもつメリットやデメリットについてより具体的に紹介していきます。
(1)事業譲渡のメリット

事業譲渡により、売り手は以下のようなメリットを得られます。
- 事業の選択と集中
- 法人格の継続的な利用
事業譲渡によって、採算の取れない部署を切り離すことができます。
たとえば、食品事業をメインに展開している会社が不振なアパレル部門を保有していた場合でも、アパレルをメイン事業とする会社にとっては販路拡大のチャンスとなりえます。
さらに、事業譲渡は会社の売却といった他のM&Aスキームとは異なり、譲渡後も法人格が失われません。
そのため、事業譲渡によって得られた売却益を元手に、残った法人格のまま別事業を行うことも可能です。
また、買い手には以下のようなメリットがあります。
- 譲受する範囲を限定できる
- 節税効果がある
株式譲渡や合併といった他のM&Aスキームでは、基本的に売り手側の保有する資産等を全て承継することになるため、簿外債務などによって想定外のリスクを負う場合があります。
しかし、事業譲渡の範囲は当事者間の契約によって決まるため、譲受したくない債務や資産などを契約段階で除外することにより、リスクを避けることができます。
また、事業譲渡によって5年間はのれんの償却を損金扱いできるため、法人税の節約を行うことができます。
(2)事業譲渡のデメリット

売り手は事業譲渡後も法人格を失いませんが、原則として、同一の市区町村内で20年間は譲渡した事業と同一の事業を行うことができません(会社法21条1項)。
そのため、事業譲渡後に別の事業を行う基盤がない場合には、事業譲渡はお勧めできません。
また、事業譲渡は、当事者双方ともに、手続きが煩雑であるというデメリットを伴います。
売り手としては、後ほど事業譲渡の流れで紹介するように、基本的には株主総会の特別決議や反対株主からの株主請求に応じる必要があります。
買い手としても、事業を譲受したのち、営業のためには別途許認可の申請が必要となったり、不動産や特許については移転登記を行う必要があります。
これらの手続きは煩雑で、時間的・金銭的コストがかかるため、事業譲渡のもつ大きなデメリットであるといえます。
とはいえ、他のM&Aスキームは事業譲渡以上に手続きにコストのかかるものも多く、事業譲渡だけが抱えるデメリットであるというわけではありません。
3.事業譲渡の流れ

事業譲渡の手続きは非常に煩雑で、かつ、高度な専門的知識と経験が必要とされます。
そのため、実際に実施するにあたっては、専門家の意見を踏まえつつ、慎重な準備が必要です。
以下からは、事業譲渡の大まかな流れについて簡単に紹介します。
専門家に依頼するにあたっても、スケジュールや進捗を把握するために、以下の流れについてはしっかりと理解しておきましょう。
(1)準備段階

売り手は事業譲渡の実施を決定すると、まずは自社の経営状況等を把握し、分析します。
交渉段階で売却金額を決定するためには、譲渡する事業の経営状況や、保有する資産などの具体的な把握が必要不可欠です。
このとき、中小企業の場合は不動産等の登記が曖昧であったり、帳簿の記載にミスがあるケースが多く見受けられます。
今後の事業譲渡の成否自体を決する大切な準備ですから、時間的余裕をもってしっかりと行うようにしましょう。
(2)交渉段階

次に売り手は、社内での準備が終わると、買い手となる譲受人を選定します。
このとき、譲受人を自力で探すことは非常に困難で労力を伴うため、M&Aに特化した仲介会社に依頼することが一般的です。
取引の相手方が見つかれば、仲介業者を通じて面談を行い、売却金額の決定や譲渡する事業内容のすり合わせなどを行います。
交渉にあたっては、これら客観的な事情だけではなく、譲渡される事業に従事する従業員との親和性などの主観的な事情についてもしっかりと確認しておく必要があります。
(3)契約段階

交渉がまとまると、当事者間での合意形成をもとに各種契約を締結します。
まずは買い手側から譲受の意思表示である意向表明書が提出されたうえ、大まかな条件を記載した基本合意書を作成します。
この合意書には独占的交渉権が内包される場合が多く、独占交渉権が設定されると、今後売り手は他の買い手候補とは一切の交渉ができなくなります。
基本合意書の作成以降、買い手はデューデリジェンスを実施します。
デューデリジェンスとは、売り手の会社の会計・財務・法務などにリスクがないかを各種専門家に調査を依頼し、最終的な買収価格を決定するために行う調査のことです。
(4)直前段階

実施に先立ち、売り手が取締役会設置会社の場合、事業譲渡を行うためには取締役会の承認決議を得る必要があります。
取締役会での決議を得たのち、両当事者は最終的な事業譲渡契約を締結します。
事業譲渡契約の作成は法的な義務ではありませんが、後日の紛争を防ぐために通常は作成されます。
契約の締結以降は両当事者は契約内容に拘束されるため、多岐にわたる書面ではありますが必ず内容を精査し、専門家からのチェックも入れるようにしましょう。
当事者の属性(売上高など)によっては、事業譲渡に関して関係省庁への届出が必要な場合があります。
また、事業譲渡を実施する際には、必ず、株主総会での特別決議を経る必要があります(会社法467条1項)。
事業譲渡の実施や株主総会の開催について通知または公告するとともに、議決権の過半数以上をもつ株主が出席する総会で3分の2以上の賛成を得られなければ、事業譲渡を行うことはできません。
これらの手続きの具体的内容は、当事会社の属性や譲渡の内容・規模によって異なるため、注意が必要です。
なお、事業譲渡に反対する株主に対しては株式の買取請求権が与えられ、事業譲渡の効力が発生する前日までの間にこの権利の行使が認められます。
(5)実施段階

事業譲渡契約に記載された期日が到来すると、対象事業が売り手から買い手へと移転します。
事業譲渡の実施に際して、買い手は不動産等の登記を書き換えるとともに、各種許認可申請が必要な場合にはこれを行います。
また、効力発生以降、買い手は従業員に対するマネジメントやシステム等の統合を行う必要があります。
この事後処理が上手くいかなければ事業譲渡自体が失敗に終わってしまうため、入念なケアが必要です。
4.事業譲渡の会計処理

事業譲渡は株式譲渡とは異なり、事業に内包される個別の具体的資産を一括して購入する手法です。
そのため、譲渡対象資産(負債も含む)のすべてを時価評価したうえ、貸借対照表へ取り込むことになります。
売り手としては譲渡対象資産の簿価を減少させ、譲渡対価との差額を売買損益として計上します。
また、譲渡対象資産のうち、消費税課税対象のものについて、借受消費税を受け取ります。
買い手としては譲渡対象資産を時価で資産計上し、対価の支払いを計上します。
また、譲渡対象資産のうち、消費税課税対象のものについて、仮払消費税を計上します。
のれん(または負ののれん)が発生する場合の処理については、こちらの記事をご覧ください。
5.事業譲渡の税務処理
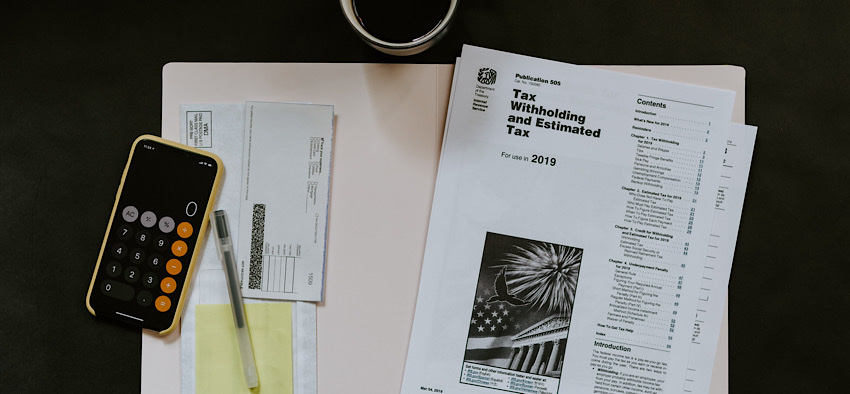
買い手は譲受した事業の資産・負債を時価で計上し、支払い対価との差額をのれん(または負ののれん)として5年間の均等償却を行います。
また、事業の譲受は消費税の課税対象となるため、譲渡される資産のなかに課税資産があれば、消費税も課税されます。
事業譲渡によって譲渡益が出た場合は法人税法上の益金として、損失が出た場合には損金として処理します。
なお、譲渡契約に基づく売却代金は当事者間で任意に決定されますが、市場価格よりも安い価格での合意の場合であっても、税務署側の時価ベースによる課税額となります。
事業譲渡においては、譲渡会社の繰越欠損金を引き継ぐことはできません。
6.事業譲渡の注意点

事業譲渡を実施するにあたっては、各種手続きを必ず法令に準拠して行うようにしましょう。
たとえば、株主総会の承認を得ずに事業譲渡が行われた場合、その譲渡は法律上当然に無効となると解されています。
そして、この無効は、譲渡当事者間のみならず株主・債権者などの利害関係人であっても、原則としていつでも主張することができるとされています。
裁判によって無効が確定すると、その譲渡は最初からなかったこととなり、財産等の移転が既に行われていた場合にはこれを元に戻さなければならなくなります。
事業譲渡では、準備段階から実施段階を通じて、法務・会計・税務について紛争や損失を生じさせるリスク要因が少なくありません。
そのため、買い手・売り手ともに、準備段階からM&Aおよび事業譲渡に特化した専門家に依頼することがおすすめです。
7.まとめ
今回は事業譲渡について、その意義やメリット、具体的な流れ等について紹介しました。
M&Aスキームとしては合併や株式譲渡などのほうが多く行われていますが、事業の一部のみを譲渡することも可能な事業譲渡には独自のメリットも多くあります。
M&Aの実施を考えている場合には、事業譲渡も選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。
















